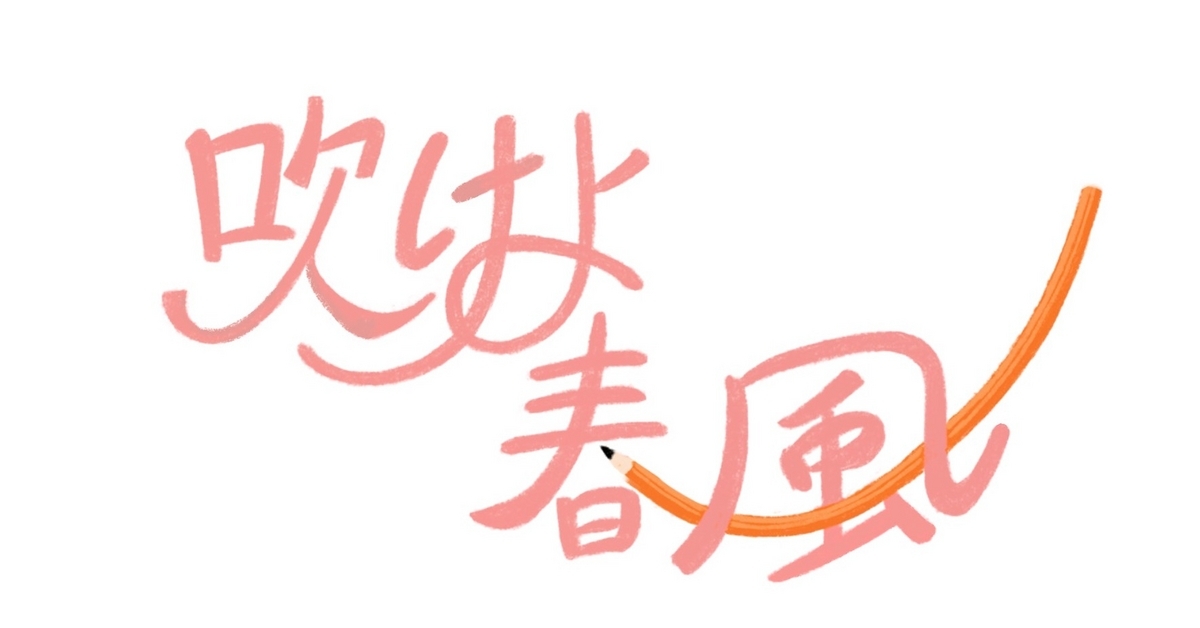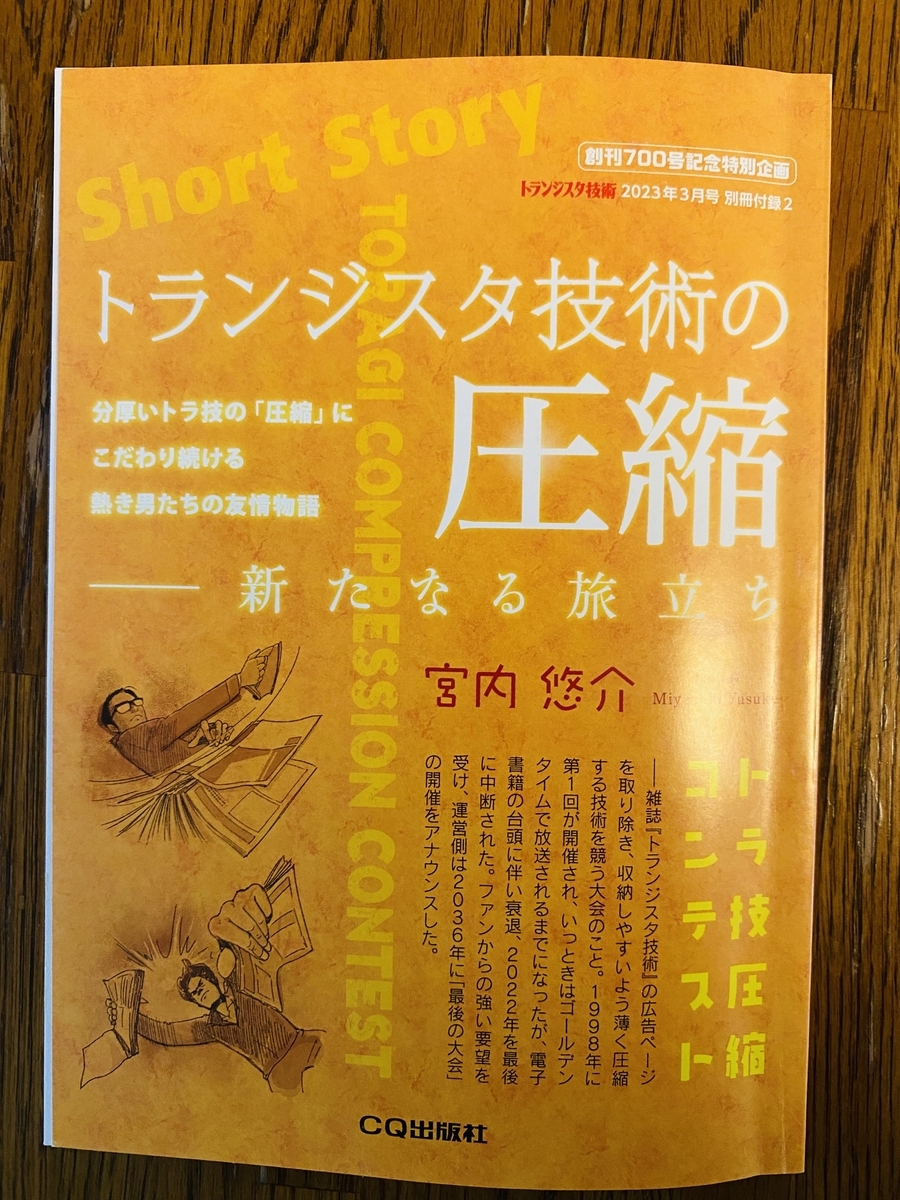0.
轟音。強風。殴りつけるような雨が顔を襲い、呼吸もままならない。私の意識はここから始まり、全く状況に理解が追いつかなかった。耐え難い頭痛。寒さと疲れで強張った足は、まともに歩みを進めてくれない。真っ暗な視界を照らすヘッドライトの光は頼りなく、体を預けていた壁をどうにかつたい歩く。小窓から明かりが漏れる分厚い木の扉を見とめ、ドアノブを回して全ての体重をかける。扉は拍子抜けするほど簡単に開き、中へ倒れ込んだ。なんとか半身を起こして、震える手で扉を押し閉じる。助かった。暖かい。安堵と共に頭痛が激しさを増し、意識を手放した。
呼びかける声に目を覚ますと、心配そうにこちらを覗き込む顔があった。見知らぬ青年だ。私は玄関で蹲ったまま気を失っていたらしく、彼は満身創痍の来訪者に戸惑っているようだった。嵐は止み、細かい雨音が小屋を包んでいた。
「すみません、避難できるのが、ここしかなくて」
私が声を絞り出すと、青年は手を差し伸べ、身体を引き起こしてくれた。そして「こちらこそ気付かなくてすみません。ここはあなたの家じゃないんですか?」と訝しげに言った。
状況をある程度把握できたのは、泥のような眠りを貪った後だった。ソファから見上げた天窓に差す光の明るさが、雨は止み、もう午後になっていることを物語る。濡れた外套は足元に丸められ、分厚い毛布に包まっていた。
青年は同じ居間のリビングチェアで眠っていたらしい。私が起きた気配で目を覚まし、重たげな瞼をこすっている。まだ20代だろう。大柄で逞しい体格だが、飾り気のない朴訥な風体をしている。歳を取ってほとんど接する機会を失った、今や遠い世界に生きる若者だ。小さな居間で差し向かうと、途端に居心地の悪さを感じた。
一方、青年は見知らぬ中年男性と2人きりでも、何ら気後れしないらしい。くだけた様子で、自分は室内で気が付いたが、この小屋のことは何も見当がつかないと話した。荷物らしい荷物もないという。私は登山ウェアを着てバックパックを背負っていたが、荷物を解いてみると所持品はごくわずかだった。激しい頭痛は治っていたものの、疲労が抜けず関節が軋む。自分についての記憶は概ね思い出せるのに、なぜ嵐の中でこの小屋の壁に縋り付いていたのか、肝心な部分が思い出せない。青年に至っては自分の名前すら分からないという。
1.
ともかく、自分たちの置かれた状況について理解する必要がある。2人で小屋の周りを確かめると、丸太組の古風で重厚な造りのおかげで、嵐に遭っても損傷はないようだった。周囲の小さな田畑は雑草に覆われ、長らく手入れされていないようだ。小屋へ続く道は1本だけで、山に向かって続いている。舗装されていないので、昨夜の荒れ狂う風雨によってひどくぬかるみ、折れた枝葉が散乱していた。
改めて明るくなった屋内を調べると、床の薄い埃を踏みしめた足跡は私たち2人分だけだった。小さなキッチン、居間と寝室、ロフトの家具類も埃まみれだ。
誰かが趣味を楽しむために使う別荘なのだろう。小さな薪ストーブ、壁にかけられた薪割りの斧、革ケースに収められたバトニングナイフ、釣りの道具、丸められたコットンタープなどが目につく場所へ綺麗に置かれていた。道具類は几帳面に手入れされ、この小屋を愛した持ち主の気配を感じる。しかし、長く使われず放置されているらしい。
整理された床下貯蔵庫には、成人男性1人なら2週間ほど過ごせる程度の保存食や調味料の類があった。医薬品、ガスカートリッジなどもある。電気やガスはないが、水道は沢の水を引いているらしい。キッチンも備えられているが、炊事は薪ストーブで補うのだろう。小屋の裏と屋内に薪が積まれていた。
ともかく、この小屋の主には後で事情を説明すればいい。青年と意見が一致したので、貯蔵庫から豆のスープ缶を取り出した。奇妙な状況で疲れ切っているにも関わらず、青年は親切で冷静だった。ごく紳士的かつさっぱりとした態度は、神経質な面のある私にはありがたかった。体格の良い彼は私以上に空腹のはずだが、必要以上に食糧を荒らしたくないからと、缶の半量だけを受け取る。空腹が不安で、無断でポケットへ忍ばせたビスケットの小袋がずっしりと重く感じる。もっと食べるように勧めても、彼は笑顔で首を振る。
この山がどの程度の高さで、今いる場所がどの位置にあるのか。山頂付近なのか、中腹なのか、舗装された国道までどれほど距離があるのか——。見渡す限り、小屋の中にはそれらを示す情報がない。2人に記憶がない以上、登山の基礎知識を持っている私がリードして、登山道を示す道標などからこの場所について探る他ないだろう。小屋へ続く道は1本だけ、迷いやすいルートではなさそうだ。何の通信機器もないが、腕時計で日時はわかる。幸いアナログなので、太陽が見えればおおよその方角も分かる。ともかく、日が高いうちに情報を掴むため、私たちは小屋から続く道を調べることにした。
小屋から離れて10分ほど進むと、昨夜の強風に折られたのか、それとも落雷にあったのか、大きな杉の木が袈裟懸けに割れて道を塞いでいた。太い枝が道の左脇にある小さな祠を押し潰し、中の石仏が割れている。倒木を跨いで進むが、道標はなく分岐もない。
道幅が狭まり、斜面に沿う小径になり、登ってまた下る。山道は谷底へ続き、美しい渓流へ辿り着いた。岩を登って流れを飛び越え、対岸から伸びる山道をまた30分ほど歩くと、不思議なことに見覚えのある倒木があった。今度は右脇に祠があり、石仏が割れている。倒木を跨いで進むと、私たちの出発した小屋が見えた。
一本道にも関わらず、どこかで道に迷ったのだろうか? しかし、もう一度道を辿ってみても、結果は同じであった。混乱のまま二度、三度と同じ道を歩くうちに私は体力が尽き、日も傾いてきた。この奇妙なルート以外には、沢登りで山頂を目指すか、或いは麓に向かうルートを歩くしかない。私たちは首を傾げながら、また小屋に戻って仮眠をとった。
翌日も軽い食事を取り、2人で山道を辿る。青年に指示を出し、手分けしてさまざまな歩き方を試したが、結果は同じだった。どうしても元の小屋へ戻ってくる。
山肌の傾斜が比較的緩いことから、標高の低い山の中腹にいるのだと思う。眺望がきかない低山では、たとえ山頂からでも周囲の山の地形を見ることができず、現在地をロストし、道迷いから遭難につながる。トレッキングコースが整備されておらず、道標がなかったり、滑落を起こすこともある。
渓流を岩づてに遡行すると大岩に行手を阻まれ、特別な装備がなければ登ることは難しい。川を下ると幅が広くなり、傾斜の付いた岩肌を奔流が走っていた。その先は剥き出しの岩肌が連なり、流れは激しい段瀑となっていく。
恐ろしく、異常な体験だった。どんなルートを歩いても小屋へ戻ってしまう。徒歩30~40分、おそらく3km程のエリアを、永遠にぐるぐる回ることしかできないのだ。
3日目、4日目……助けを借りて傾斜をよじ登り、山肌を辿って山頂を目指そうともした。落ち葉が積もっていて足元が悪く、うまく登れそうもなかった。多少は山歩きを経験している私がリードして、この状況から抜け出さねばと焦るが、なんの進展もない。それでも毎日次の予定をたて、粘り強く探索を続けた。
私たちが何らかの事故によって遭難しているのなら、とっくに捜索が開始されているはずなのだ。それなのに、冬の山々は毎日同じように静かで、ヘリや防災無線の音はしない。時折聞こえる鳥の声の他は、何の気配も感じられない。
この奇妙な状況を受け入れることができず、また食糧がなくなる恐怖と不安から、私は追い詰められていた。食べ物がほとんど喉を通らなくなり、憔悴しきっていた。口を挟もうとする青年を叱責し、指示に従うよう懇願する。夜も眠れない。体力の限り山のルート探索を続けたが、10日目の深夜に高熱を出した。
異変を察知すると、青年はこれまで使わなかった寝室を掃除して、私のために寝床を整えてくれた。肩を借りてベッドに入ると、今度は粥状に崩した豆のスープを少しずつ飲ませ、介抱してくれる。残り少ない食料を、消化しやすく工夫してくれたらしい。そのままグッタリと眠りに落ち、目を覚ました頃には体調が落ち着いていた。
ドアをノックする音がして、また青年が寝室を覗く。心配そうな顔にはあどけなさの名残りがある。ベッドの傍へ腰掛けた彼と静かな食事を終えると、彼は今後の方針について話し始めた。
十分なカロリーを摂取せず、疲れも取れない状態で山の散策を続けると、不注意になって怪我や滑落の危険がある。居間のソファと寝袋で簡易的に休息を取ることを止め、小屋を掃除して、落ち着いて生活したほうが良い。そのために、私が今使っている寝室と、ロフトを各自のスペースとして振り分け、ゆっくり体を休められるようにする。
また、控えた消費を試みてきたとはいえ、貯蔵庫の食糧は残り少ない。山で食糧の確保を試みつつ、なるべく小屋から離れずに捜索隊へのSOS発信を行うべきではないかと。
全くもって正論だった。なぜ山の経験者である私から、もっと早く同じ提案をできなかったのだろう。焦りと恐怖によってこの数日を無駄にし、迷惑をかけてしまったことを詫びたが、彼は微笑んで許してくれた。
水が充分にあるので、食糧の消費はまだある程度抑えられるだろう。しかし、小屋全体を暖めるストーブの火を絶やすわけにはいくまい。小屋周辺には間伐後に放置されたらしい木々があり、少し歩けば大きな倒木もある。長期戦を覚悟した以上は、まず薪の確保から……。これからの作業を考えている間に、外から乾いた音が聞こえた。
居間にあった薪割り斧を振るう音だろう。発熱の名残りで軋む関節をさすりながらキッチンへ移動すると、窓から外で薪を割る青年が見えた。同じように燃料の確保を考えたのだろう。先んじて行動してくれている。冬晴れの空の下、黙々と斧を振るっている。逞しい腕で長い柄を握り、器用に薪を割っては放り投げ、庭の隅へ積み上げていく。その表情は穏やかで、何の恐れも迷いもないようだった。
私は、私は一体、何をしているのか。
自分よりもずっと若い彼とこの山に閉じ込められたまま、ジワジワと命の危険に晒されつつある。思えば2日目には山を出られないとわかり、3日目には捜索隊の気配がないことにも気付いていた。それなのに、私は自分の恐れや怯えのまま、頑なに山を歩き回ることを続けた。小屋そのものを不気味に感じて、使えるものをロクに使わず、居間での仮眠を続けて体力を消耗させた。私は山の経験者であり、年長者でありながら、今日まで青年のためには何も行動しなかった。
結果、体力を温存しつつ小屋へ滞在するという決断を遅らせ、時間を無駄にしてしまった。今日になって諭されるまで、私は無駄な悪あがきに気づくことすらできなかった。
窓の外で黙々と斧を振るう青年の傍には、雑木林から運んできたらしい丸太が積み上げられている。この10日で弱り、痩せ衰えた私があれを運んだら、彼の3倍は時間がかかるだろう。そして斧を振り薪を作るとなれば、尚更……。
喉の奥から羞恥と情けなさが湧き出し、涙腺を伝って、幾筋も目頭から溢れた。
後悔や不安で鬱々とした私に、青年が明るい話題を与えてくれたのは、その夜の食事のときだった。ロフトの片隅から、何冊かの書籍を見つけたのだという。釣りの指南書、罠猟の解説書、そしてポケット野草図鑑。開いてみると、何度も歩き回った冬の山道で見かけていた草花が「食べられる野草」として載っていたのだ。私の浅い登山知識では、野草の見分け方や調理法といったサバイバル分野は補えなかった。長期戦に耐えうる強い武器を発見した安堵で、私たちは久しぶりに笑い合った。
翌日からはそれまでと一変した“生活”が始まった。
小屋を修繕し、調理器具や倉庫の道具をあらため、手入れする。放置された間伐木から丸太を少しずつ切り出し、運び、割って、薪にしてゆく。2人で山道を散策して、野草を探す。青年は図鑑を手に、植物を注意深く観察して同定した。毒性や薬効を声に出して読み上げ、野草から取れるビタミンやミネラルに注目しようという。腹の足しにはならなくても、体調管理には役立つというわけだ。
雪もなく、冬の終わりが近づいていることが幸いして、ノビルやフユイチゴ、川沿いでセリが採取できた。全滅させないよう少しずつ摘み取り、茶などに加工できそうな野草も選り分けていった。
小屋にあった釣り道具は、テンカラという伝統的な技法の毛バリ釣りで使うものらしい。渓流を遡行しながらテンポよく短い竿を振り、毛バリをポイントに投げ、魚が食いついた瞬間に素早く引き上げる。指南書に従って渓流を観察すると、目の良い青年がいくつもポイントを発見してくれた。警戒心の強い川魚たちは人間の姿に気付くと岩陰に身を潜めてしまうらしい。川に近づく段階から慎重なアプローチを取る必要がある。作戦を話し合いながら歩いていると、山肌に獣道と小動物の新しいフンを見つけた。原始的なくくり罠の作り方を調べて、獣道へ設置してみた。
これまで絶望的な気分で眺めてきた山々の表情が一変した。冬山にも実りがあり、さまざまな生き物の気配があった。いざ生活のフィールドとして山と川を観察すると、そこは絶望的な閉鎖空間などではなく、いくつものヒントに溢れ、広がりのある場所だった。また、青年は体力があるだけでなく、とても頭が良い。手に入れた書籍の内容をあっという間に覚え込み、要領よく実践し、勘所を掴んで応用していく。
翌日からは、朝夕の時間帯を罠の確認と釣りに充てるため、彼は日中に行う作業のルーティン化してくれた。弱った私は主に野草の採取を担当し、小屋の番をする。狼煙がわりに生木を焼きながら、飲み水を沸かし、道具や衣類の煮沸など簡単な家事をこなす。青年が早朝に山の見回りを終え、昼から薪を割る。共に食事を作り、日が暮れる前には揃って山を回り、ルートに変化がないか調べる。食糧が充分ではないぶん、睡眠をなるべく多く取る。
日ごと太陽の高度が増し、少しずつ日中の気温が上がっている。体調の良い日は青年とともに渓流へ赴き、釣り竿を振るった。日当たりの良い斜面にタンポポやフキノトウが現れ、キクイモを見つけた。頻繁に鹿の鳴き声が響き、近づいてくる春を知らせる。
春が来れば、もっと食べられるものが増えていくだろう。この山からいつ出られるのかという不安の一方で、ここでの暮らしに希望が見え始めていた。
たった一人の同居人が、素晴らしく頼もしい人物であることが心からありがたく、ほとんど役に立たない私自身が不甲斐ない。しかし、私を惨めな気分にさせる青年に、わずかな苦々しさも感じるのだ。
2.
初対面の印象から全く変わることなく、24時間365日を善良に過ごせる人間というものが、世の中にどれほどいるのだろう。
この山で長期間過ごすことを覚悟して2週間が経った。恐ろしく身体感覚が優れている青年のおかげで、釣果が上がりはじめ、ヤマメやイワナを何匹か手に入れることができた。青年はできる限り保存食にしようと言うが、貯蔵庫の食糧がほとんど尽き果てた今、私は不安のあまり提案に応じられずにいた。このまま永遠に救助が来ないのではないか。食糧の確保が間に合わず、飢えて死ぬのではないか。ならば今食べた方がいい。
私は老いて疲れていて、青年と同じ様には動けない。無理をすれば翌日体が悲鳴を上げ、気温が下がれば関節がこわばる。自分で教えたことを間違うこともあれば、2人で決めたルーティンを覚えていられないこともある。体力を温存したつもりでも疲れが残り、疲れ切っても眠りにつけない。その度に苛立ち、心の余裕を失ってしまう。
しかし、彼は常に安定している。明るく親切で、私の不調を見逃さずに声をかけ、気遣ってくれる。どこまでも尽きることがないかのように体力が溢れ、どんな時も前向きで、私と柔和に接してくれる。こんなに完璧な人間が、この世にいるものだろうか?
今日も彼が薪を割ってくれている。寒さの中でも熱を発して汗ばむ、屈強で健康な身体。労働の疲れから一晩で回復できる若さ。不安定な日々でもルーティンを守る誠実さ。気さくで前向きでいられる余裕を持った心。純粋で真っすぐな、晴れ渡った空のように曇りのない、度量の大きな人格。
全て私には備わっていない、もしくはかつて持っていたとしても、とっくに失われたものだ。彼の太陽のように輝くエネルギーに照らされ、その熱を分けてもらって、この日々を生きながらえている。
28日目。夕刻から降り始めた雨が激しくなる中、私は薪ストーブの前で長考していた。青年は先にロフトへ引っ込み、静かな寝息を立てている。春を前にして雨が一晩降れば、草木は一斉に芽を出すだろう。土に付いた人間の気配を洗い流し、罠に獣がかかるかもしれない。飢えを凌ぎながらやり過ごす日々も、もう少しはマシに——。そこまで考えたときに、大きな雷が鳴った。稲光が一瞬室内を明るく照らし、同時に私の脳裏へ、何の根拠もない予感をもたらした。
雨はますます勢いづく。私は外套を羽織り、バックパックを背負って、ヘッドライトを頼りに山道を進む。真っ暗でほとんど視界がないが、それでもほとんど毎日歩いている道だ。どうせ迷うこともない。普段の何倍も時間がかかったが、そこへ辿り着いた。
小さな祠。祠は潰される前の姿でそこにある。細いしめ縄をかけられた石仏も、割れずにそこにある。
どういうことなんだ? 近寄って手を伸ばしたとき、閃光が目を焼いた。轟音。後退りその場を離れようとしたが既に遅く、倒れてきた杉の木の枝先が唸りをつけて頭を強かに打ち付けた。
呼びかける声に目を覚ますと、心配そうにこちらを覗き込む顔があった。私は小屋の玄関でびしょ濡れのまま蹲っていて、彼は満身創痍の私を心配しているようだった。嵐は止み、細かい雨音が小屋を包み込んでいた。
安堵した私が声を絞り出すより先に、青年は手を差し伸べ「気付かなくてすみません。ここはあなたの家じゃないんですか?」と言った。
3.
ここまで私の取り止めのない述懐に付き合ってくれたことを嬉しく思う。そこから私が彼と過ごした醜悪な日々について、もう少し書き続けるのを許してほしい。
二度目の嵐、正しくは二度目の「一夜目の嵐」の後、私は青年とともにまた山小屋とその周辺を調べた。貯蔵庫の食糧や薪の数は以前と同数に戻り、部屋は埃にまみれ、畑は荒れていた。道は倒木に塞がれ、祠は潰れていた。そして、一本道は小屋へ向かってループしているのだった。
青年はこの小屋で過ごした28日間をまるで覚えていなかった。記憶を失ったのではなく、その身なりや様子から28日前に戻ってしまったらしい。しかし私は全て覚えている。窓に映る顔は以前よりもげっそりと痩せ、汚れ、やつれていた。
この小屋では私を除いて、道だけではなく時間もループするらしい。思いもしなかったことに愕然としたが、それでも私は、充分に揃った貯蔵庫の食糧を前に、涙が出るほど安堵した。状況を理解していない青年と一緒に懐かしい豆のスープを平らげ、私が体験したこの28日間について説明しようとして——言い淀んだ。
時間が巻き戻ったのであれば、彼は私と出会ってまだ半日ほどしか経っていない。見ず知らずの人間に「この山からは出られない。君はこれからこの小屋で私と2人っきりで暮らしていくんだ」と言われて、どう思うのか。説明を諦め、ともかくもう一度この山を調べることにした。何度も山道を辿り、渓流を遡上する。出られないと知りながら、山からの脱出を試み、失敗をやり直し、青年と共に動揺を装う。
そうしているうちに、胸の内に暗い欲望が湧き上がってきたのだ。極めて卑しく、浅ましく、くだらない欲望だった。
小屋へ戻るなり、私は青年に「小屋からは3kmと離れられないようだね」と話した。そしてこの異常な環境では、探索ばかり続けても体力を無駄に消耗するのだから、長期戦を覚悟して小屋で安全に過ごすことを提案した。
疲れを取るためにそれぞれがゆっくり眠れる自室を持つことにしよう。捜索隊に見つけてもらうため、日中は生木を燻して煙を上げつつ、山から食べられるものを調達しよう。そうやって、協力し合い、なんとかこの山で生き延びようではないか。
思った通り、頭の良い彼は提案の合理性をよく理解して、賛成してくれた。そして冷静沈着な私に深く感謝してくれたのだ。礼には及ばないと彼の肩を叩き、ロフトを自室に使っても良いかと聞いた。快く応じた青年に感謝を伝えて、階段を上がる。そして書籍を探し出し、全て自分のバックパックへ入れた。
バックパックの中の書籍は、かすむ目を擦りながら一人で読み込んだ。野草採集、罠の確認、渓流で釣りのポイント探し。さまざまなことを彼に教えながら、毎日一緒に山を散策する。山菜の栄養素や毒性や薬効について詳しく教え、保存食の大切さを説く。
利発な青年は私が何を教えても注意深く聞き入り、笑顔で感謝してくれた。一度の説明すれば完璧に理解して、素直に実践する。毎日のルーティンを欠かさずこなしながら、力を使う作業を率先してサポートしてくれた。
10日目には、私たちは共にテンカラ釣りの釣果を上げた。さらに食べきれない魚を塩漬けにして、保存できるまでに上達した。獣道の見つけ方も分かるようになり、何度かの失敗のあと、20日目にして遂にアナグマが罠へかかった。
初めての狩猟。早朝の山に響き渡るほどの歓声を上げ、山に感謝した。青年も笑いながら喜び、肩を抱き合った。もはや山暮らしの上級者だ。
知識は私から彼に伝えることに意味がある。いくら虚勢を張り、取り繕っても、彼という人間の輝きには叶わないし、肩を並べられるわけでもない。しかし、若く美しく、心根の良い若者が、博識で経験豊富な年長者を敬い従う。この健全な関係がなければ社会は成立し得ないのではないか?
どちらかが極端に優れていたのでは、力関係のバランスが崩れ、一方が自信を失ってしまう。今回は私の工夫によって、互いの人間的価値の釣り合いが取れた。彼から同情や哀れみの目ではなく、尊敬の眼差しを向けられた。そして共に挑戦と失敗を繰り返し、技術を身につけた。これこそが順を追った正しい関係性であり、あるべき自然の姿なのではないか。
しかし、私たちが山の暮らしに順応したところで、嵐はまたやってくる。
4.
3度目の嵐の日。やはり午後から雨足が強まり、風が唸り始めた。
私は夕食時から長考していた。前回の予感に従うのならば、今夜は青年と共に山へ向かって、倒木から祠とその中の石仏を避難させるべきだろう。しかし、そのことを彼にどう説明すればいい? なぜ私が今夜は激しい嵐になることを知っていて、その嵐から何を守るべきかを知っているのか。こればかりは「博識な先生」というだけでは説明がつかない。
食糧を適切に管理してきた今、28日目も温めた豆のスープと干し魚にありついている。盗む必要がなかったビスケットを2枚ずつ分け、パンの代わりに添えた。クロモジの葉を煎じた甘やかな香りのお茶が湯気を立てている。質素極まりないが、滋養と安心のある食卓だ。うるさく屋根や窓を叩く雨風の音とは裏腹に、静かな食卓で私は不思議と満たされていた。テーブル越しに青年の方を見やると、彼もこちらへ視線を寄越した。特に会話をするわけではないが、穏やかな眼差しだ。
ストーブで暖められた、雨風に晒されることのない小屋の中。安全な居場所で、信頼できる人間と2人、自らの力で手に入れた食事を得られていることに、深い感謝の気持ちが湧き起こる。
この食事を終えたら、暖かい部屋から出ず、今夜も寝室のベッドで眠りにつくのはどうか。明日にはまた1日目の荒れた小屋で目が覚めるのかもしれない。しかし前回と同じく、私だけが時間の巻き戻りを起こさず、記憶を保っていられるのならば——。
付け焼き刃の知識ではあったが、今回は彼の足を引っ張るのではなく、協力者として生活を営むための努力ができた。憔悴して衰弱し、守ってもらうのではなく、自分の仕事を理解し、全うできた。
では、次回はより一層上手く、彼とここで生活できるのではないだろうか。次はもっと彼と話し、協力し合って、釣りや狩猟の工夫をして、たくさんの保存食を作ってみたい。簡単な食事だけでなく、手の込んだ料理に挑戦してみるのはどうか。山の散策をもっと注意深く行い、素材を得て、燻製や発酵食を試してみては。ツタや樹皮、動物の皮を加工して、山の見回りを便利にする道具を作ってみるのも……。
食事の手が止まっていることを心配され、我に返った。一体何を血迷っていたのだろう。もしこのまま28日間を繰り返すのなら、この山には永遠に春が来ないのだ。目の前にいる青年と、共にこの山を出ることを夢見ながら、もうすぐ春がきたらと語り合いながら、私は私の意思で、繰り返す冬の日々に彼を閉じ込め、終わらない遊びに付き合わせることになる。
説明は諦め、また彼が眠ったのを見計らって外へ出た。雨はますます激しく、鋭い冷えが手や足先の感覚を奪う。ヘッドライト、そして時折の稲光を頼りに山道を進む。
やはり祠は元の姿でそこにあった。倒木の前に石仏をどうにかしなければ。小さく手を合わせたあと、腕を回し抱えてみるが、ずっしりと重くて叶わない。強い雨で手元が滑り、ぬかるんだ土が足元を不安定にさせる。膝や腰を庇いながら踏ん張り、遂に石仏を持ち上げたところで空が白く光った。
轟音。強風。殴りつけるような雨が顔を襲い、呼吸もままならない。左足に激痛を感じるが、体を動かすことができない。辺りを見回すと、辛くも直撃を免れた倒木と寄り添うようにして伏せっていたらしい。石仏は割れて足元に転がっている。手を滑らせ、地面に埋まった石に当たって、砕けてしまったのだろう。私の足先と共に。
意識を失っていたようだ。目を覚ますと、心配そうにこちらを覗き込む顔があった。見知った顔だ。私は玄関でびしょ濡れのまま蹲っていて、彼は重傷者が転がり込んで来たことに戸惑っているようだった。嵐は止み、細かい雨音が小屋を包み込んでいた。青年は手を差し伸べ、私の身体を起こしてくれた。そして「気付かなくてすみません。ここはあなたの家でしょうか?」と訝しげに聞いた。
「ええ、ここは私の小屋です」
思わぬことが口をつき、続きの嘘は考えるよりも先に発せられた。
「久しぶりに別荘へ滞在しようと思って来たのですが、怪我をしてしまって。あなた、もし遭難してしまったなら、あるものは何でも好きに使ってください。私はこの通りですから、ここで助けが来るのを待ちましょう」
気の優しい青年は、私の怪我をいたく気遣ってくれた。湯を沸かしてたらいに溜め、足を洗ってくれるという。気を使わなくてもいいと固辞したが、彼は私を座らせた。日焼けした無骨な手が、数ヶ月の汚れでボロボロになった足をさする。怪我をした箇所を触らないよう、痩せて皺の寄った皮膚を撫で、慎重に指を解し、湯をかけて温める。骨の状態は分からないが、腫れ上がった足の痛みは鈍痛に変わっていた。血流に合わせてドクドクと痛みが体を走り、私を苛む。その苦痛よりも、青年の美しい大きな手が私に触れていることが辛かった。足を浸した湯よりも、皮膚を通して伝わる体温が熱く感じられる。私の汚れて傷ついた足を、健康で美しい青年に洗わせる。それは、私が彼に対して暗に強いた奉仕そのものに思えた。
怪我をした足を固定して人心地がつくと、私が知るこの山の不可思議な事情を全て彼に語って聞かせた。冬の終わりの山で生き延びる術を全て開陳し、何よりロフトに仕舞われている書籍を活用するよう伝えた。
そして、私は非常に神経質な人間であると説明した。生活を厳密に分け、できる限り話しかけないこと。決して寝室に入らないことを彼に約束させた。
貯蔵庫の保存食を半分寝室に持ち込み、ドアを閉め、鍵をかける。左足にまた激痛が走る。怪我をしてしまった以上、これまで2人で試みてきたことが、今回はできない。私の回復力では、この先自然に元の状態まで治ることも期待できないだろう。
5.
もしも、人生で最後の手紙を、人生で最後の友人にしたためることがあったなら、そこへ愛について書かないのは不自然なことのように思える。人は愛によって産まれ、生かされ、また愛によって焼かれ、命を奪われるのだから。私もまた、枯れて乾いた心が愛によって引火し、大きく燃え上がらせたのだ。しかしこうして筆を取り、君に伝える言葉を探すと、愛とはあまりに陳腐な言葉で、伝えるべき私の想いとはかけ離れたもののように感じる。君がどれほど素晴らしく、これから長く生きていくべき人間であるか。この冬を乗り越え、春を感じ、夏を迎えるべき人間であるか。決まりきった言葉にはとても収められない。ただの間に合わせ、仮初の生活であった私たちの日々を、正しい方向へ導き、更には人生においてかけがえのない時間に変えてくれたこと。真に尊敬しうる人間との素晴らしい生活を経験させてくれたことへの感謝を、私はどのように書けばいいのだろう。私は自分自身の内奥に潜む感情に、喜びを見出す暇もなく蓋をしていた。それでも尚、君の輝きは隣人の心に炎を灯し、眠っていた血を熱くたぎらせる力があった。完璧に幸福で満たされたテーブルを囲んだ、そのたった一晩の記憶。それを抱えて私はこの先も生き続けられるし、死ぬことができる。おそらく、多くの人が君の帰りを待っているのだろう。太陽無くして季節は巡らず、降雨無しに作物は実らない。君という輝く太陽を、この小さな世界に閉じ込めておくには忍びないのだ。どうか、多くの人を照らし、導いてほしい。ただの別れの言葉がこんなに長くなってしまった。それでも伝えたい感謝の思いの大きさとは程遠い。枯葉の想いなど考えたことはなかったが、次に枝を賑わせる艶やかな緑の新芽を思えば、枝から落ちる瞬間さえ感謝に満ち、幸福であることを、君は知っているだろうか。手紙の結びでは送る相手に神の加護を望むべきかもしれないが、君にはそれすら必要がないように思える。君は祝福そのものだ。この長い冬を抜け、君に春がやってくる世界であるように。私が願うことはそれだけだ。
長々とした記憶と記録。その終わりを一息に書きつけてから、青年がこれを読んだところでほとんど意味がわからないことに気が付いた。今回の彼にとって、私は自身の小屋へ遭難者の滞在を許した寡黙な山男なのだ。これまでのことを書き留め、彼に伝えたところで何になるというのだろう。
ノートは残り1ページ。長々と叙情詩を書く余裕はない。夕方から益々強まった雨が屋根や窓を忙しなく叩いている。
「用事があるので小屋を離れる。心配する必要はないので、君は小屋にいるように」
それだけを書き付け、ページを破って折り畳んだ。
28日間、ほとんどベッドから出ず、青年となるべく顔を合わせなかった。会話も拒否したので、最初の1日以降は彼がどのように過ごしたのか知らない。
立ち上がると、飢えと貧血が眩暈を呼んだ。萎えた足で壁をつたい歩き、居間を覗くと、綺麗に手入れされているようだった。貯蔵庫を開けると、魚や肉が塩漬けで保管されている。私の思惑通り、彼1人の28日間は完璧なものだったらしい。
テーブルにメモを置いた。窓の外の雨はますます勢いづく。私は外套を羽織り、バックパックを背負う。
足をもつれさせながら分厚い木の扉にすがり、ドアノブを回して全ての体重をかける。風の抵抗を受けながら、嵐の中で山道を辿る。真っ暗な視界を照らすヘッドライトの光は頼りなく、まともに歩みを進められない。殴りつけるような雨が顔を襲い、呼吸もままならない。強風。轟音。
----------
あとがき
「吹けよ春風」4年目突入おめでとうございます!
去年はドタバタしているうちに寄稿できずじまいだったのですが、今年は更にボリュームアップしたようで、本当に相馬くんはすごくて偉いですね。またお声がけいただけて嬉しいです。
カワウソはどうしていたのかというと、2021年の発行号では「キャンプの正面玄関から入る」という、趣味のキャンプを楽しんでますよ〜みたいな記事を書いてました。その後、関東エリアの小さい山小屋を購入し、移住支援金の対象になるからと気軽に山へ移住し、都内と2拠点生活を始めました。ところが思いのほか山の生活が面白く、畑をいじったり、猟師さんの手伝いに行って鹿を解体したり、里山の手入れに参加したり、畑を荒らす猿の群れと戦ったりして、山小屋が本拠地みたいになりました。で、2022年頭にギャルみたいな猫が山小屋にやってきて、もうLOVEすぎてほぼ山にいるので、ずっと絶対に取りたくなかった車の免許を根性出して取得しました。不思議な力で車を手に入れ、車があるから行動範囲も広がったしイケるやろと思って、仕事もほぼほぼ山エリアに関するものにシフトしました。色々あって1台目の車を破壊して2台目を購入、その後も毎日100kmくらい運転して山じゅう走り回ったりして、後はちょいちょい都内に帰ってBarの店番続けたりツイキャス配信やったりして、今に至ります。
なんかいつの間にか人生の急ハンドルを切って、もう今年で3年目に突入しようとしてる感じで......改めて書くと、一体何をしているんだ???えっ......?何これ???
それで、まぁ今回も「吹けよ春風」に寄稿するんなら、そういうムチャクチャな近況を書こうかな〜〜という気でいたんですが、こないだあの、世界の大球技大会があって。
例の「森の中の丸太小屋」のコピペ本当にいいよな〜〜完全版の小説が読みたいなと思って、誰か書いてないのかあるやろと思ったら、どうも無いっぽくて。そういえば、己がほぼ森の中の丸太小屋に住んでるやんけと思って、これに至ります。
なんかBLみたいなん書いたろ!と思ったのに夢小説みたいになったし、ChatGPTに手伝ってもらおうと思ったら解釈違いを起こすし、しゃあなし書き進めたら1万字を超えてしまった。これのディティールを書くために山小屋生活を送ってきたのかもしれません。
何のとは言いませんが、春季キャンプというものは2月いっぱい行われて、春が来ないうちに終わるということと、ログハウスとLogを掛けてあります。
これで本懐を遂げましたので、来年は山小屋からもっと違う環境にいるのかもしれない。ドバイとか新天地にいるのかもしれないから、そうしたらまた近況を書きますね。
ここまで読む人いるのかな?読んでくれたなら、サンキュ!Bye-Bye!

カワウソ祭
https://twitter.com/otter_fes
山と里を往復しながら、人に化けて暮らすカワウソ。Twitterをやったり文章を書いたり、酒が好きなのでバーの店番をしたり、後は酒を飲んで楽しく暮らしています。そして山で鹿を解体したりしている。何これ?酒うってくんろ。